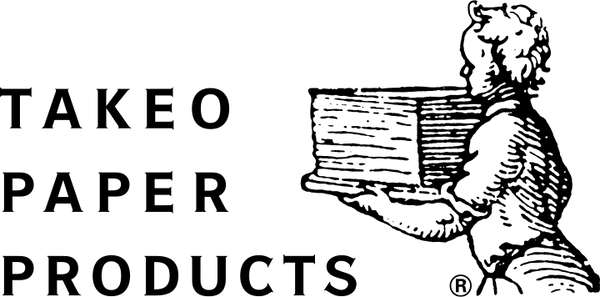型染の工程
和紙に染色する型染は民芸運動に端を発した日本の伝統的な染色技法で、全ての工程が手仕事により行われます。
型紙を用いて紙に防染糊(ぼうせんのり)を置き、染色した後水洗いをして糊を落として制作しています。
使用される和紙はこんにゃく糊を塗布し、耐水性を加えた手漉きの和紙を使用しています。

1. 型掘り
トレーシングペーパーに書き写した下絵を型紙に貼り付け、図柄をカッターで切り抜いていきます。
細かい部分や柄が独立している部分は「つなぎ」という細い線を残し、図柄が落ちないようにします。
型紙は和紙に柿渋(かきしぶ)を塗ったものを使用しています。


2. 紗張り
絹糸でできた「紗(しゃ)」という網目状の布をラッカーで型紙に貼って補強した後、図柄の「つなぎ」を切り落とします。



3. 糊置き
こんにゃく糊をひいた和紙に型紙をのせ、米粉とぬかを混ぜて蒸したものを練った「防染糊(ぼうせんのり)」をヘラでのばしていきます。

4. 色差し
糊置きが終わり乾燥させた和紙に豆汁(ごじる)を混ぜた顔料や染料を防染糊がついていない部分に差していきます。
豆汁を混ぜることにより、水にさらしても色が落ちにくくなります。

5. 水元
顔料や染料が乾いた後、糊を落とす為に水に浸し、防染糊を刷毛などで洗い落とします。

6. 乾燥
水を切った後、良く乾かして完成です。